心不全とは病名ではなく心臓は栄養分や酸素を含んだ血液を全身に送り出すポンプの働きしています。
このポンプの働きが低下して血液を十分に送られなくなっ状態をいいます。心不全は心臓が弱った状態のことです。
おこり方は ①急性心不全 ②慢性心不全 ③慢性心不全 の急性増悪に分けられ、
また左心不全と右心不全にも分類されます。
症状はおおまかに ①肺うっ血症状(左心不全・呼吸困難)
②体静脈うっ血症状(右心不全・むくみ)
③心拍出量低下(心臓の働き低下・倦怠感)
心不全の原因は左心不全が心筋梗塞、右心不全が肺血栓塞栓症があげられ緊急の対応が必要です。
誘因は呼吸器感染症がもっとも多く、不整脈・狭心症・・・がつづきます。
心不全の検査・診断は症状、診断結果と胸部X線撮影や血液検査、心電図により可能で
さらに心エコー検査・運動負荷試験・RI検査・心臓カテーテル検査・冠動脈造影検査が必要です。
心不全の一般的な治療は安静、水分制限、塩分制限のほか薬物治療があり、
原因別治療(心不全の原因の除去)は急性心筋梗塞症が風船療法で詰まっている冠動脈を再開通させたり、
心臓弁網膜症に対して手術を行うことなどができます。
予防方法は①心不全の原因となる疾患にならないこと
(心筋梗塞症ならないように禁煙・減塩・低脂肪・肥満防止・適度な運動に心がけること)
②心不全となれば悪化誘因を防ぐこと(ベスト体重の維持・水分制限や塩分制限を守り、
服薬すること・風邪注意・医師の診察を定期に受けること))です。
心筋梗塞・狭心症(虚血性心疾患)は動脈硬化で冠動脈の内側が狭くなり血管のけいれんで血液が十分に
心臓の筋肉にいきわたらなくなった時心臓は酸欠状態となることです。
また心筋の「心臓の電気信号」を伝える働きにも障害をきたし心室細動という重大な不整脈を起こすことがあります。
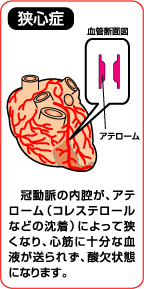
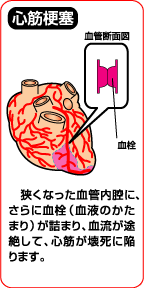
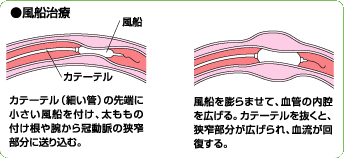
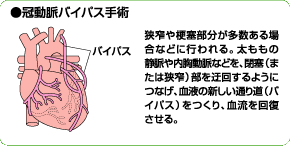
薬で発作を抑える
ニトログリセリン錠やカルシウム拮抗薬など、血管を広げる薬が用いる。なかでも硝酸薬の舌下錠は、効き目が非常に速く、
発作時に使うと狭心症は治まる。皮膚にはって、皮膚から薬を吸収させる貼付薬もある。貼付薬は効き目が長いあいだ続くので、
寝る前に貼っておけば朝の発作を防ぐことができる。
生活習慣を改善する
狭心症では、日常生活上の注意も重要。とくに労作性狭心症は、どのようなときに発作が起きるかを本人がよく知って、
その誘因を避けること。一般には、節度ある生活を心がけ・運動のしすぎ・精神的興奮・食べすぎ・飲みすぎを避ける・禁煙・
十分に休養・睡眠をとる・虚血性心疾患を防ぐ生活を心がける
対応可能な病院に入院することが第一
心筋梗塞の発作が起こったときはもちろん、その疑いがありそうなときもがまんしたりせず、ためらうことなく
CCU(冠動脈疾患の集中監視と治療体制を備えた設備)があるなどの対応可能な病院に入院を。急性心筋梗塞の場合、
数時間から1~3日のうちに致命的な事態が起こることが多いので、早ければ早いほど、救命率が上がる。
発症してから1か月以内の急性期を乗りこえれば、かなり安定した状態になるので、
できる条件がととのっている患者さんには外科的手術も行われる。
脳卒中とは脳の血管が詰たり破れたりして栄養が届かなくなり、細胞が死んでしまう病気。急に倒れて意識がなくなったり
半身マヒが起きたりろれつが回らなくなったりします。前触れが起きることもあります。
発見が早ければ治療やリハビリで回復しますが遅ければ回復が難しくなります。
タイプとして脳梗塞・脳出血・くも膜下出血がある
脳梗塞は脳を養う血管が詰まるタイプで①脳の太い血管の内側にコレステロール固まりでき動脈を塞ぐアテローム血栓症梗塞
②脳の細い血管に動脈硬化が起き詰まるラクナ梗塞
③心臓にできた血栓が流れてきて出来る心原性脳塞栓症(脳卒中死亡の6割以上)。
脳出血は脳の中の細い血管が破れて出血し神経細胞が死んでしまうタイプで
高血圧や脳の血管が弱くなり破れる原因が多い(脳卒中死亡の2.5割)。
くも膜下出血は脳をおおっている3層の膜のうち、くも膜と軟幕の間にある動脈瘤が破れ脳全体を圧迫する。
突然の激しい頭痛・嘔吐・けいれんが起き意識がなくなり急死することもある(脳卒中死亡の1割)。
リハビリが肝心になります
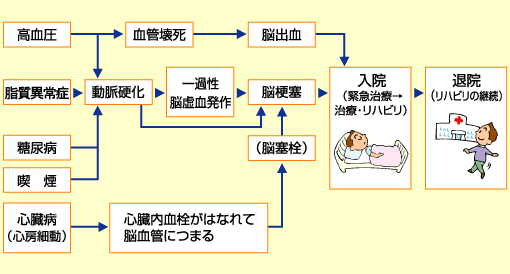
CT・MRI・MRAなどによる脳中の画像検査や脳ドックや健康診断で判る。
早めに生活習慣危険因子(煙草・運動不足・肥満・大量飲酒・ストレス発散)を見直すことや
高血圧・脂質異常症・糖尿病・心臓病(心房細動)で予防できる。
食生活の改善(減塩・薄味・カロリー過多防止・コレステロール管理)
脳卒中の治療法としては血栓を作りにくくする薬を使う、
動脈硬化が明らかな場合は手術を行うこともある。
はじめに次のことを確認し救急車を呼ぶ。
①意識があるかどうか ②呼吸をしているかどうか ③吐いていないかどうか。
吐きそうだったら横向きに寝かせる。救急隊の人が来たら発作から今までのようすを伝える。